
集まれ! 世界のロイヤル・アニマル! 王室と犬と猫の歴史
世界中の王室で、犬や猫が文化や歴史を象徴する存在として大切に扱われてきました。 国を超えて愛されてきた彼らの歴史は、動物たちが人とともに歩んできた足跡がより鮮明に見えてくるようです。今回は各国の王室が迎えてきた犬たち、猫たちからその背景にある価値観や文化をみていきましょう。
ペットともっと深く理解し合うために、動物の生態や行動学、飼育方法から最新トレンド、法律・社会問題まで幅広い知識をお届けします。 犬猫だけでなく、フェレットやカワウソなど珍しいペットに関する情報や、AI・SNSを活用した新しい楽しみ方も紹介中。 ペットとの暮らしを豊かにする教養を身につけましょう。

世界中の王室で、犬や猫が文化や歴史を象徴する存在として大切に扱われてきました。 国を超えて愛されてきた彼らの歴史は、動物たちが人とともに歩んできた足跡がより鮮明に見えてくるようです。今回は各国の王室が迎えてきた犬たち、猫たちからその背景にある価値観や文化をみていきましょう。

いつだったか「笑う犬の~」という大人気バラエティ番組がありましたが、実際の犬はどうでしょうか。 遊んでいるとき、リラックスしているとき、ふと口角が上がったように見えたことはありませんか?これは専門用語で「社会的微笑(social smile)」と呼ばれ、肯定的な情動と関係していると考えられています。

日本の妖怪伝承のなかで、猫ほど多彩に描かれてきた動物はいません。 夜の闇に光る瞳、しなやかな動き、どこか人の心を見透かすようなふるまい。 そんな猫は、古くから「神聖かつ妖しい存在」として人々に恐れられ、敬われてきました。

自然界の理はいつの世も弱肉強食。 しかし、必ずしも体の大きいものが強いとも限らず、どんなに小さく、弱い存在でも、いざとなれば思いがけない力を発揮することがあります。 その心理を端的に表した言葉が、「窮鼠猫を噛む(きゅうそねこをかむ)」。

シンプルな構成とちょうどいいくだらなさが光るアメリカン・ジョーク。 そして、犬をテーマにしたジョークは、英語圏では「Dog Jokes(ドッグ・ジョーク)」としてひとつのジャンルになっています。 今回は、有名なものからマニアックなものまで、明日からさっそく使える30のドッグ・ジョークをご紹介します。
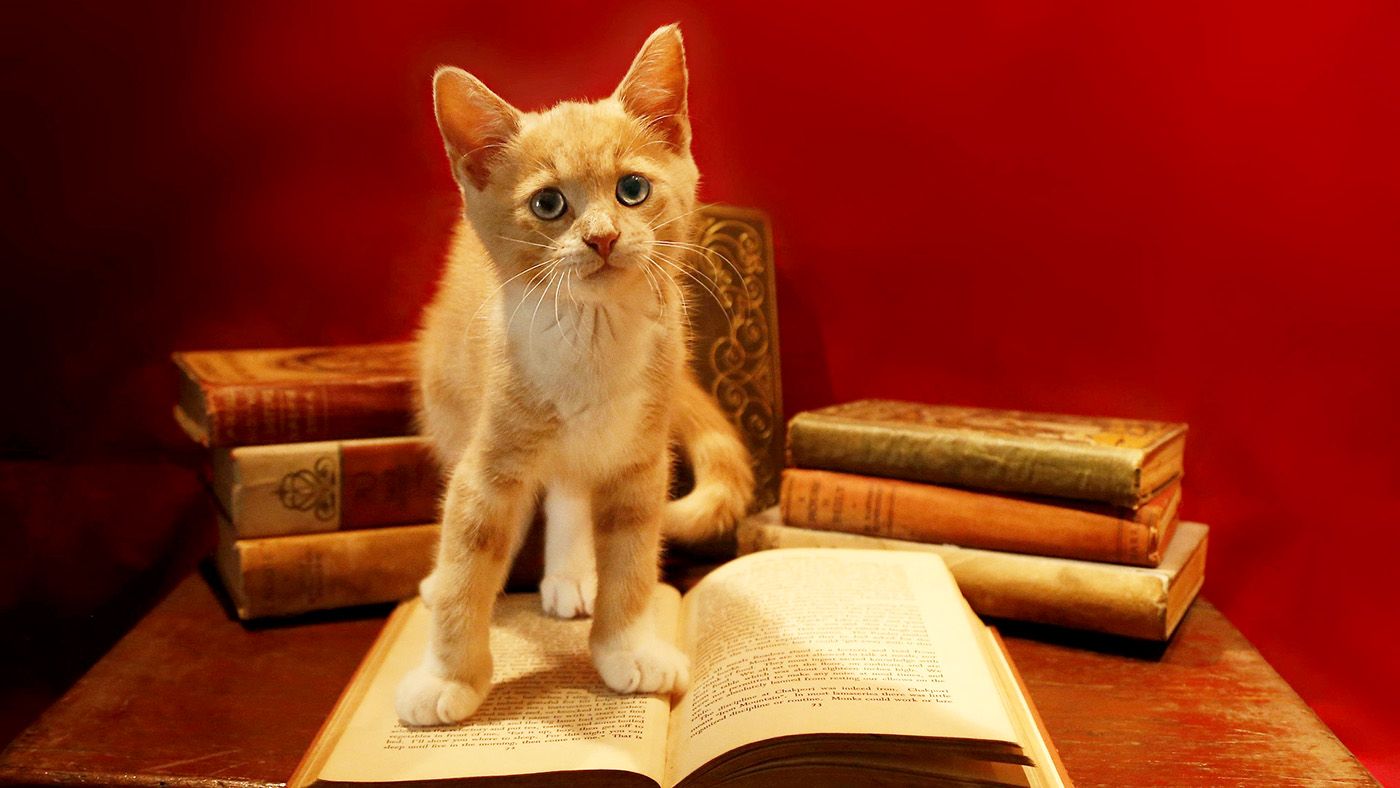
犬や猫は古くから人の生活に寄り添ってきた動物。 そのため日々の暮らしや自然の移ろいのなかで、わたしたち人は彼らの行動を観察し、そこから教訓や風情を見いだしてきました。そうして生まれたのが「ことわざ」や「俗信」と呼ばれる言い習わしの表現です。

猫といえば、クールでマイペースな動物。 しかし、本当に信頼している相手にだけ見せる特別なサインはご存知ですか?今回は、愛猫たちが大好きなあなたにだけ見せる9つの特別な行動をご紹介します。 それぞれの仕草の意味を知ることで、より愛猫と心を通わせてください。

犬の世界は日進月歩。 昔は「純血種こそ理想」と考えられていましたが、少し前からはミックス犬という新しい価値観が広がっています。 チワプー、チワックス、マルプーなど、聞き慣れた名前も多いのではないんでしょうか。
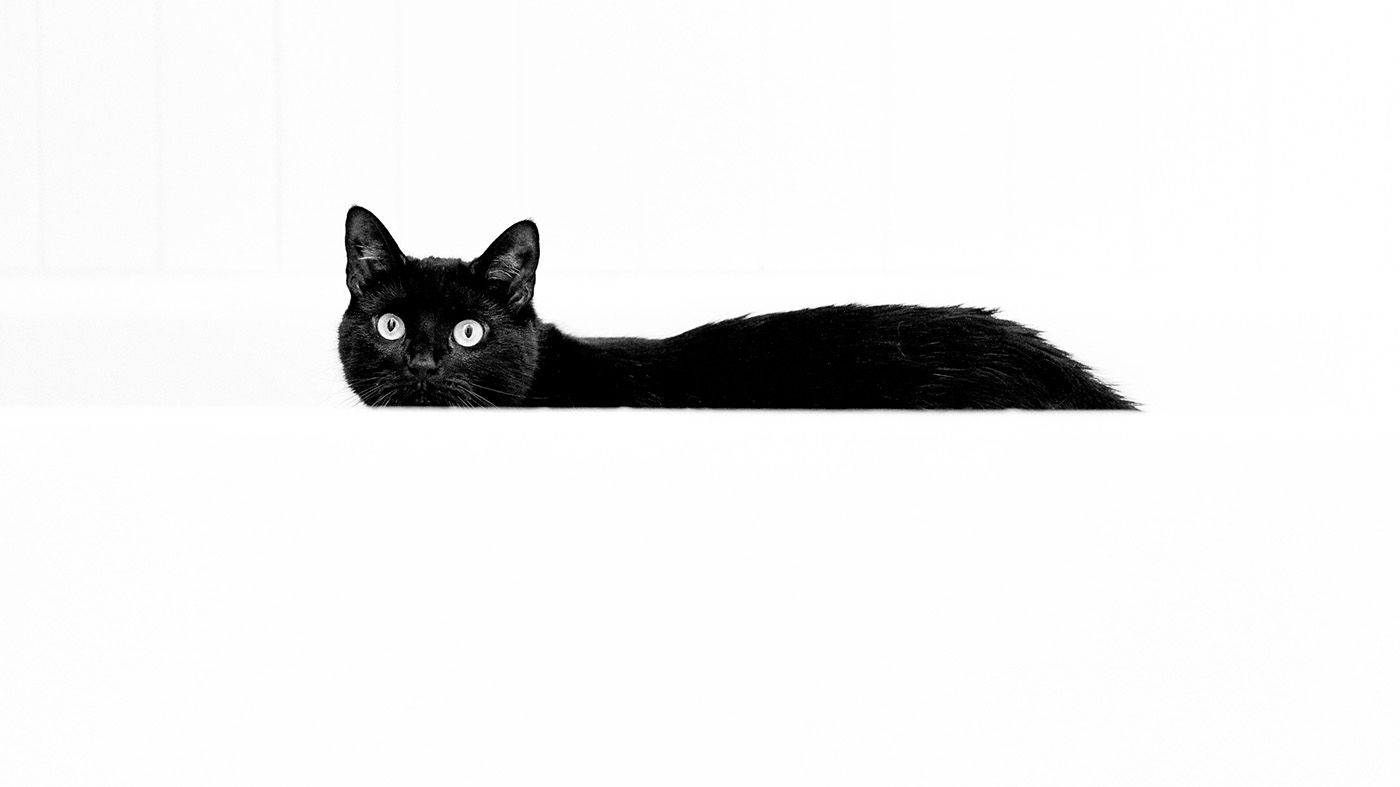
ハロウィンが近づくと、街の装飾やイラストにたびたび登場するのが「黒猫」。 しかし、なぜ黒猫は「魔女の使い」「不吉の象徴」として語られるようになったのでしょうか。その背景には、古代の信仰、中世ヨーロッパの迷信、そして近代日本の文化輸入という3つの時代の流れが関係しています。

猫と暮らしていると、ふとした瞬間にじっと見つめられることがありませんか? 実は、あのまっすぐな瞳の奥にはいくつもの感情が込められています。その中でも特に知られているのが「スローブリンク(Slow Blink)」と呼ばれる動作。 これは単なるまばたきではなく、猫からの愛情と信頼のサインに他なりません。

オーディオ機器でお馴染みのビクター。 そして、そのシンボルロゴには蓄音機と犬の姿。あまりに有名なこのシンボルロゴにまつわるエピソードはご存知でしょうか?犬の名はニッパー(Nipper)。 19世紀に実在した犬で、ひとりの画家と、亡き主人の声が生み出した感動的なストーリーの主人公です。

漢字を学んだ日本人であれば、中国語でも雰囲気で読める……とはさすがにいきませんが、おおよそのニュアンスが掴めるのも確か。 では、慣れ親しんだ「犬種名」であれば、どの程度想像できるでしょう。意外と難しいのが、中国の犬種名は音訳(発音を漢字に当てはめる方法)と意訳(意味をそのまま表す方法) の両方が混在するところです。

日本には島国特有の不思議な生き物がたくさんいますが、その中でも神秘的な存在として知られているのがオオサンショウウオです。 大きな体と原始的な姿は、初めて見た人を驚かせるに違いありません。今回は、オオサンショウウオの基本的な特徴とその歴史、民間伝承、さらにはその仲間たちとの関係まで幅広くご紹介します。

月が変わって10月になり、早いもので今年も残すところ3か月。 日本、そして世界では動物に関連する数多くの記念日が制定されています。 それぞれの記念日には制定の経緯や日付に込められた意味があり、動物福祉や環境保全を考えるきっかけにもなります。

猫にとって特別な存在である「マタタビ」。 与えるとゴロゴロ転がったり、体をすり寄せたり、時には走り回るような姿を見せることから、古くから「猫にマタタビ」という言葉が使われてきました。 しかし、私たち人にとって、マタタビという果実はなかなか目にする機会も少なく、未知の部分も大きいのではないでしょうか。

渋谷のランドマークとして今や知らない人はいない「忠犬ハチ公」。 駅前の銅像は待ち合わせ場所としておなじみですが、そのエピソードを細かに把握している人は意外と少ないのではないでしょうか。今回は、忠犬ハチ公の生涯と上野英三郎博士との絆、戦争と再建を経た銅像の歴史をご紹介します。

侘び寂びと呼ばれる日本独特の美意識は、季節の移ろいや一見言葉にしがたい情景までも表現してきました。 そしてその感性は、古くから人の隣人として寄り添ってきた猫の模様にまで息づいています。たとえば、「茶トラ」や「ハチワレ」といった親しみやすい呼び名は、日常の中で生まれた日本らしい表現といえます。

猫と暮らしていると、ふと不思議な仕草を見せることがあります。 そのひとつが「頭突き」。 愛猫が飼い主に向かってゴツンと頭を押しつけてきたり、家具や壁に軽く頭を当てたりする様子を見て、思わず首をかしげたことはありませんか?