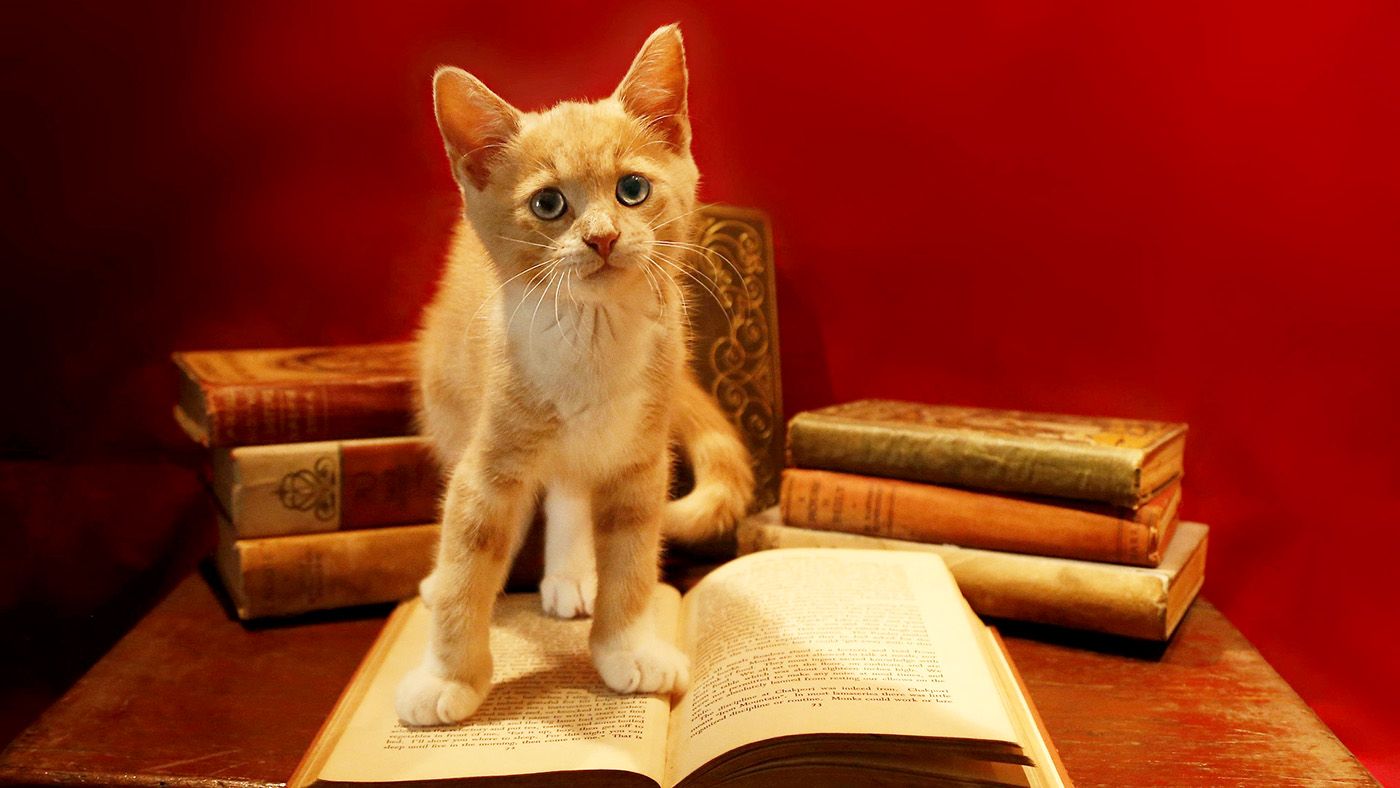【完全保存版】愛犬・愛猫と避難するための大地震対策ガイド

2025年7月、とある漫画家の予言も手伝って、日本各地で改めて大地震への備えが注目されています。
かつて日本を襲った阪神淡路大震災・東日本大震災・熊本地震のような大規模災害では、人と同様にペットの命を守る行動も求められます。
今回は、犬や猫と暮らす飼い主のために「ペット同伴での避難行動」を時系列でシミュレーションしてみましょう。
地震発生前の備えから、避難所生活、そして復興への道のりまで実践的なポイントを一つずつご紹介します。
日ごろの備えがすべてを左右する地震発生前
災害時、最も重要になるのは「備え」です。
とくにペットを連れて安全に避難するには、より多くの準備が求められます。
しつけ・健康管理を日常から
大声で吠えたり、暴れたりしてしまうと不安が蔓延する避難所で受け入れてもらえないケースも。
「お座り」「待て」「おいで」などの基本的なしつけは、いざという時の行動制御に必要不可欠です。
また、クレートやキャリーバッグに慣れておくことも大切です。
日頃から安心して過ごせる空間として認識させましょう。
さらに、つぎのような健康管理も必須です。
- ワクチンやノミ・ダニの予防
- 不妊・去勢手術の検討(避難所でのトラブル防止)
- マイクロチップや迷子札の装着(迷子対策)
Loading...
ペット用の非常持ち出し袋を整えよう
人間用と別に、ペット専用の持ち出し袋を用意しておくと安心です。
中身の目安はつぎのとおりです。
- 食べ慣れたフードと飲み水(5日〜7日分)
- 折りたたみ食器・給水器
- 予備のリードや首輪、ハーネス
- 薬や療法食(持病がある場合は多めに処方してもらう)
- トイレ用品(シート、スプレー、袋など)
- タオル・毛布・おもちゃ・おやつ
- ペットの写真(迷子時の手がかりに)
- ワクチン証明書や健康手帳
- 犬の場合は鑑札・狂犬病予防注射済票
すぐに取り出せるよう、玄関や避難口の近くに保管しておきましょう。
避難場所と避難ルートの確認
地震時には、通れる道や安全な場所が限られます。
日頃からハザードマップを確認し、「どの道を通ってどこに向かうか」を家族全員で共有しておきましょう。
Loading...
また、ペット同伴可能な避難所の確認も必須です。
すべての避難所がペット受け入れに対応しているわけではないため、代替案として以下のような選択肢も検討しましょう。
- 親戚や友人宅
- ペットと泊まれるホテル
- 車中泊
地域とのつながりも防災の一部
近所の方と日頃から交流をもち、「ペットと一緒に暮らしている」ことを伝えておくことも防災の一環です。
万が一の際には、お互い助け合える関係が大きな支えになります。
Loading...
地震発生直後の安全確保
地震発生直後、まずは自分自身の身を守ることが第一です。
丈夫な机の下に入り、頭を守りながらペットを守りましょう。
- 小型犬や猫
- 抱きかかえて一緒にしゃがむ
- 大型犬
- リードを短く持ち、ケージがある場合は倒れないよう支える
パニックになっても、できる限り落ち着いて行動することがペットの不安軽減につながります。
揺れがおさまったら確認すること
- 火の元(ガス、ブレーカー)を確認
- ペットが無事か確認
- 玄関や窓の施錠で脱走防止
興奮状態のペットは突発的に飛び出すことがあります。
この段階でリードやハーネスを装着しておくと安心です。
避難準備から避難行動までの判断
テレビ、ラジオ、スマートフォンなどで地震情報や避難指示を確認しましょう。
停電や通信障害に備え、電池式のラジオがあると心強いです。
状況に応じて冷静に判断できるよう努めてください。
ペットの避難準備を整える
- ハーネス・リードの装着
- クレート・キャリーバッグへの収容
- 持ち出し袋の再確認
- 水や食料もすぐに持ち出せるようまとめる
飼い主自身も、動きやすい服装と両手が空くリュックを装備してください。
可能であれば近隣住民にも声をかけ、安否確認や情報共有を行いましょう。
安全な経路での移動
地震の後は道路や構造物の損壊が予想されます。
ハザードマップを頼りに、倒壊・土砂災害・津波の危険が少ない道を選びましょう。
- ブロック塀や電柱には近づかない
- 地割れや液状化に注意
- 橋やトンネルは避ける
できれば複数人で行動し、互いに助け合いながら進みます。
ペットとの避難中のマナー
- リードを短く持ち、他人に迷惑をかけないように
- 原則としてクレートやキャリーから出さない
- 排泄物は適切に処理し、清潔を保つ
- すれ違う人には一声かけるなど、周囲への配慮も忘れずに
周辺の人に配慮した避難所生活
避難所では「人とペットの生活スペース」が分けられていることが一般的です。
互いに快適に過ごすため、ルールの順守が求められます。
ペットの生活管理
- ケージ・クレート内での生活が基本
- 鳴き声や臭いなど周囲への配慮
- 散歩時もリードは必ず装着
- 排泄物は速やかに処理
- 食事・給水は所定の時間・場所で行う
- マナーベルトやオムツの利用(特にオス犬)
- 異常な鳴き声・下痢・食欲不振などがあれば獣医師や担当者に相談
スキンシップや声かけは、ペットのストレス軽減につながります。
避難所のペット担当者や他の飼い主と情報交換を積極的に行いましょう。
飼い主自身の健康管理も忘れずに
- 手洗い・うがいの徹底
- 十分な水分・食事・睡眠
- 不安を感じたら相談する
避難所ではお互い助け合いながら、役割分担や清掃活動などにも協力していきましょう。
復旧・復興に向けて
復興に向けた仮設住宅やみなし仮設では、ペット同伴の可否やルールが施設ごとに異なります。
入居前に確認し、近隣への配慮ある飼育環境を整えましょう。
自宅に戻る場合も、耐震性や安全性をしっかり確認する必要があります。
防災意識をアップデート
今回の避難経験を振り返り、足りなかった備品の補充やしつけの見直しなど、今後の防災対策に活かしましょう。
環境省の「ペットの災害対策」のページも情報がわかりやすくまとまっているため参考にしてみてください。
常日頃から備えることが最大の防災です。
大切な命を守るために今日からできること
予言はさておき、大地震はいつ起きるかわかりませんし、いつ起きても不思議はありません。
ですが、備えによって被害を減らすことはできます。
ペットは大切な家族の一員。
避難の難しさはありますが、適切な準備と行動で一緒に乗り越えることは可能です。
この記事があなたの「備えるきっかけ」になることを願っています。
- 2025.08.11
- 2025.07.04