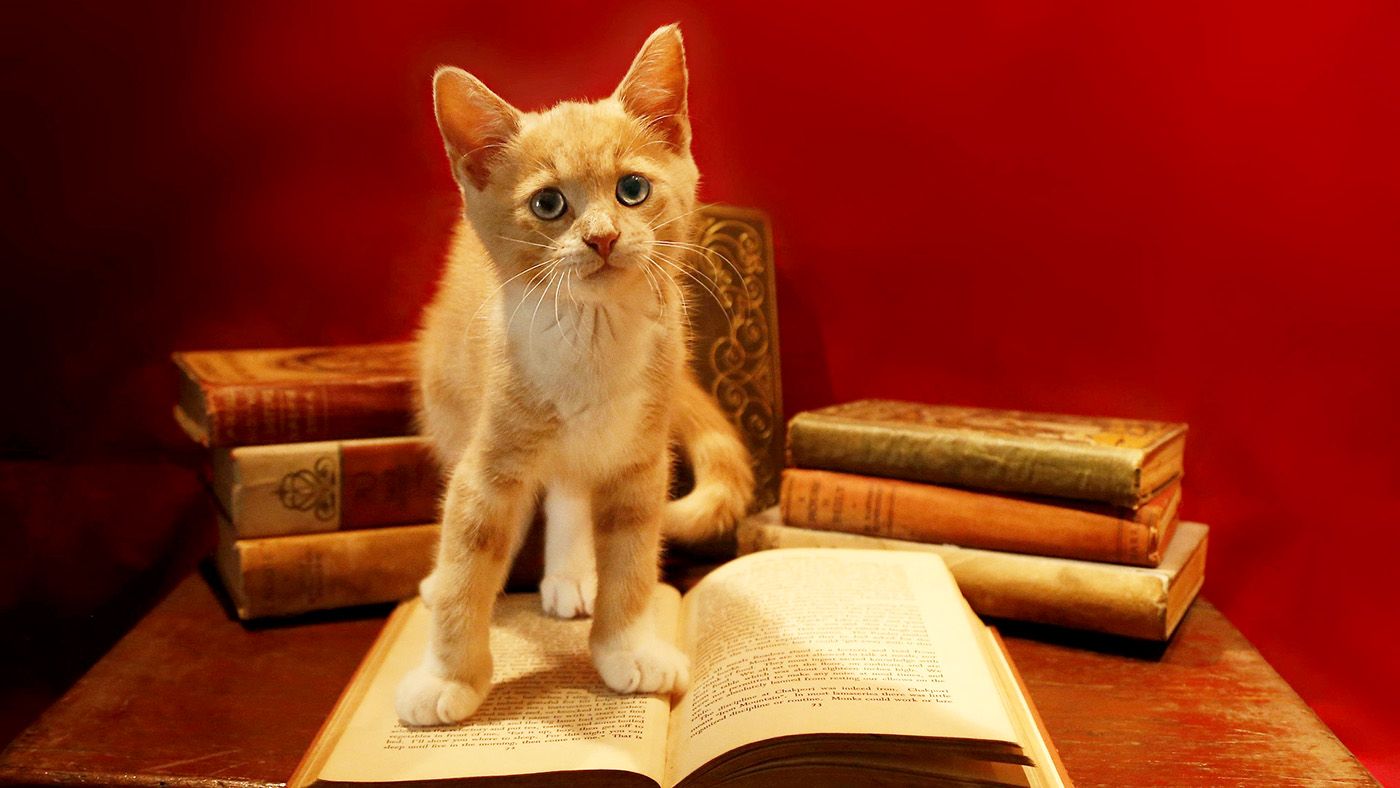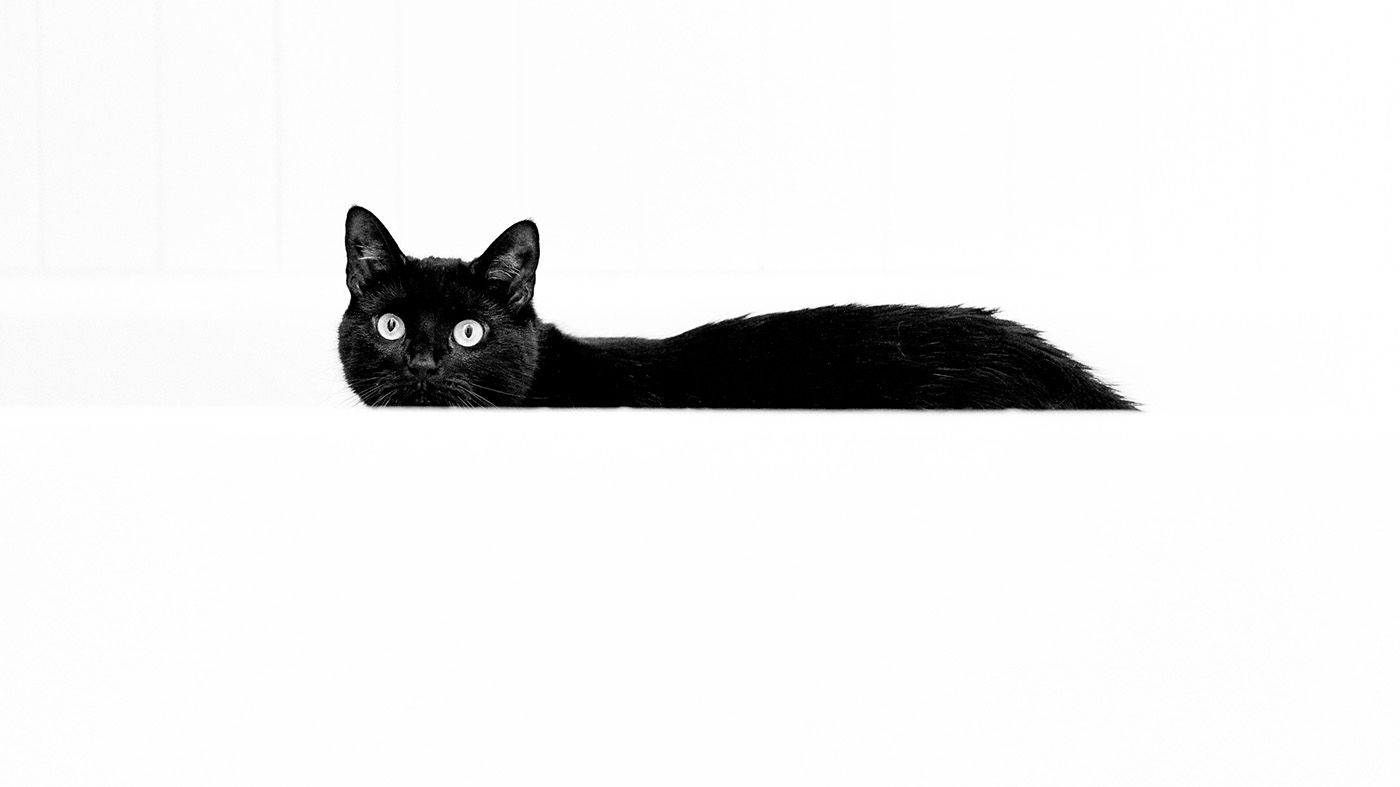猫の目の見え方を解説! 視野角や色覚とオッドアイの謎

猫の目は、人間の目とは構造も機能も大きく異なります。
広い視野角や暗所での高い視力や色の見え方の違いなど、その特徴はまさにハンター仕様です。
今回は、猫の視界の特徴から年齢による変化、瞳孔や目の色の違い、オッドアイの見え方までを詳しくご紹介します。
猫の視野角と立体視
猫の視野角はおよそ200〜220度。
これは人間の約180度より広く、横方向の動きに敏感であることを意味します。
ただ、両目で立体的に物を捉えられる範囲(両眼視野)は120度前後と、人間よりやや狭め。
そのため、遠くの物を立体的に捉えるのはやや苦手ですが、横方向で動く獲物を察知する能力は非常に優れています。
ハンティングに特化した視界と言えるでしょう。
猫の色覚は二色型
猫の視覚は完全なモノクロではありません。
青系と緑系の色は認識できますが、赤系の色は見分けにくい二色型色覚。
赤やピンクは灰色や黄味がかった色に見えていると考えられています。
このため、赤いおもちゃよりも青や緑のおもちゃのほうが反応が良いこともあります。
ただし、猫は色よりも動きや形の変化に反応するため、色の差が行動に大きな影響を与えるわけではありません。
暗所視力は人間の約6倍
猫の網膜には「桿体細胞(かんたいさいぼう)」という暗所に強い視細胞が多く存在します。
そのため、暗闇でも人間の約6倍の感度を持ち、暗い視界の中でも行動が可能です。
さらに、網膜の裏側にはタペタム(輝膜)と呼ばれる反射板のような構造があります。
これが光を反射し、再び網膜に送り込むことで暗所視力を強化します。
夜に猫の目が光るのは、このタペタムの反射によるものです。
年齢による視力の変化
子猫は生後10日ほどで目が開きますが、最初はぼんやりとしか見えていません。
光の変化や動く影には反応しますが、細かい形はまだ認識できません。
生後2〜3か月頃になると視力が発達し、距離感や反応速度が高まります。
この時期は遊びを通して狩りの練習をしているようなものです。
一方、高齢猫では白内障や網膜変性、緑内障などで視力が低下することがあります。
視野が狭くなったり、夜間でも見づらくなったりするため、この期間は家具の配置を変えないなどの配慮が必要です。
また、加齢により瞳孔の動きが鈍くなり、光量調整がしづらくなることもあります。
瞳孔の動きと見え方
猫の瞳孔は環境や感情に応じて大きく変化します。
明るい場所では細くスリット状に、暗い場所ではまん丸に開きます。
明るいときは被写界深度が深くなり、近くから遠くまでくっきり見えます。
暗いときは多くの光を取り込めますが、ピントが合う範囲は狭くなり、静止している細かい物はやや見えにくくなります。
また、恐怖や興奮でも瞳孔は大きく開きます。
これは光量の問題ではなく、周囲の情報を一気に取り込み、危険や獲物を逃さないための反応です。
目の色と見え方の違い
猫の目の色は虹彩のメラニン量で決まり、青、緑、黄色、琥珀色などがあります。
色の違いが直接的に視界の色味や解像度を変えるわけではありませんが、光への感受性には影響します。
メラニンが少ない青い目の猫は、強い光にやや敏感です。
逆に、黄色や琥珀色の目は光を遮る力が強く、日中の眩しさに比較的強い傾向があります。
ただし、この差は日常で顕著に感じられるほどではありません。
オッドアイの見え方
オッドアイとは左右の目の色が異なる状態。
オッドアイの場合でも、視力や色覚はほぼ同じと言われています。
ただし、白猫でオッドアイの片方が青い場合、その青い側の目に先天的な聴覚障害が伴うケースがあります。
これは視覚ではなく聴覚に関する問題ですが、片側からの刺激に対する反応が遅れる場合があります。
また、左右の目で光の透過率や眩しさの感じ方がわずかに異なることもあります。
片方が青で片方が琥珀色の場合、強い光の下では青い目のほうが瞳孔が縮まりやすい傾向があると報告されています。
猫の視界を理解して生活に活かす
猫の見え方を理解することは、暮らしの中での配慮や遊び方の工夫に役立ちます。
高い暗所視力を活かした遊びは夕方や早朝に取り入れると良く、色は青や緑を意識すると興味を引きやすくなります。
高齢になれば環境の変化を最小限にし、視覚以外の感覚を頼れる工夫を取り入れることが大切です。
例えば、匂いや音で食事やトイレの位置を知らせるなど、五感全体を使ったサポートが有効です。
猫は人間とは異なる世界を見ていますが、その能力は長い歴史の中で猫が生きやすいように進化してきたもの。
猫の視界を理解して、より快適で安全な生活環境を整えてあげましょう。
- 2025.08.12