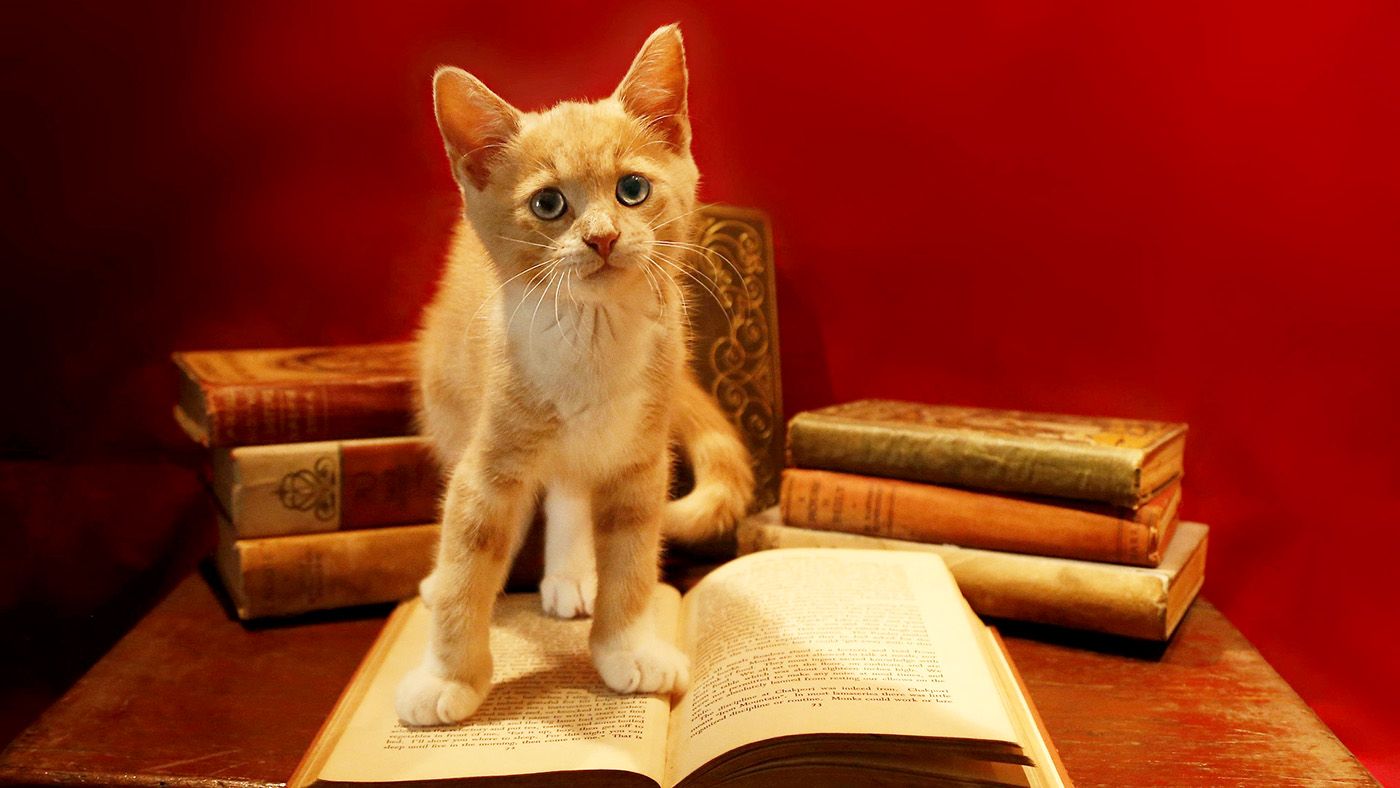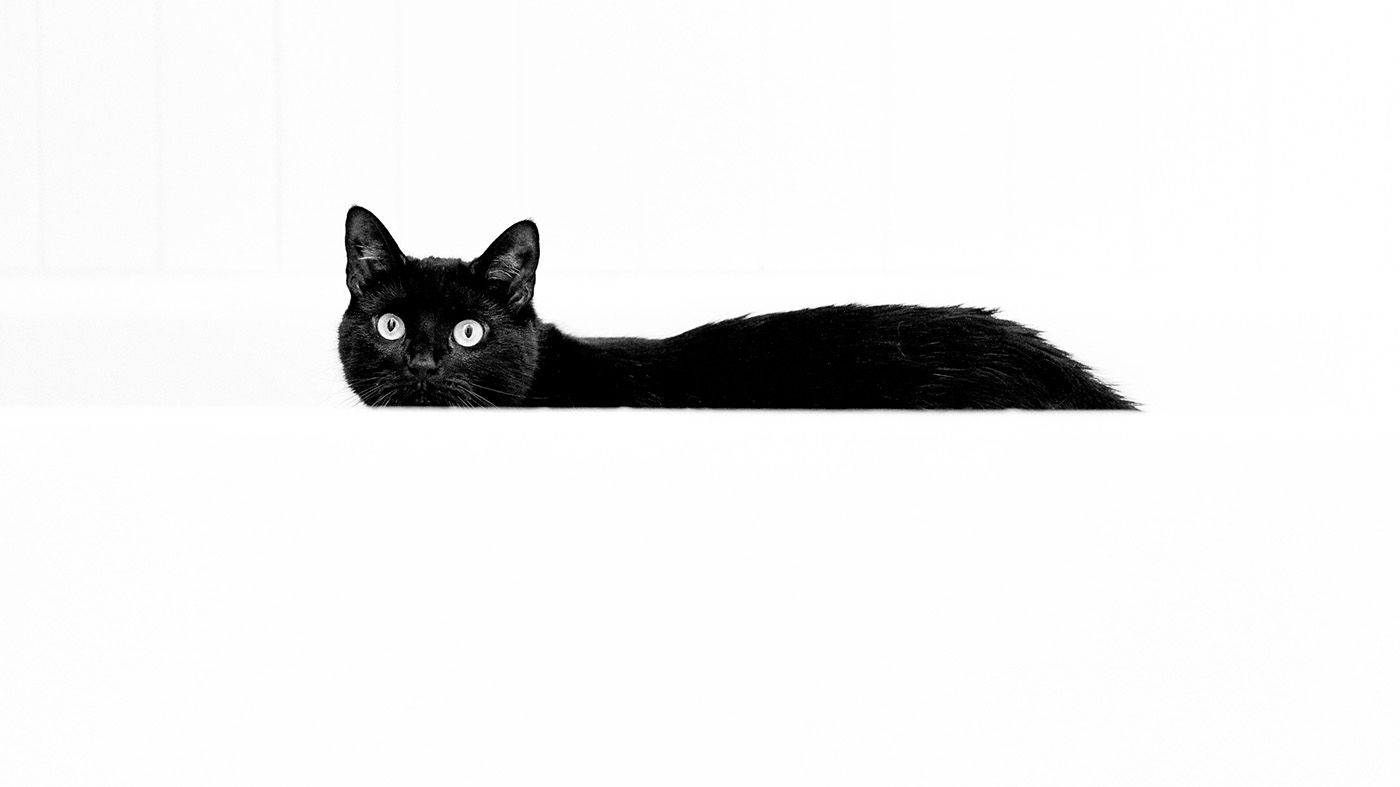猫にマタタビの効果と安全性は? 正しい与え方と注意点

猫にとって特別な存在である「マタタビ」。
与えるとゴロゴロ転がったり、体をすり寄せたり、時には走り回るような姿を見せることから、古くから「猫にマタタビ」という言葉が使われてきました。
しかし、私たち人にとって、マタタビという果実はなかなか目にする機会も少なく、未知の部分も大きいのではないでしょうか。
今回は、マタタビという植物の正体と猫への作用、安全な楽しみ方、そしてリスクまでをわかりやすくご紹介します。
マタタビはキウイの一種

マタタビは、マタタビ科マタタビ属に属するつる性落葉植物で、英語で「Silver Vine(シルバー・ヴァイン)」、学名を「Actinidia polygama」といいます。 身近なフルーツ「キウイ」の仲間でもあり、北は北海道、南は九州まで日本中の山地に自生する植物です。
マタタビの特徴は、夏になると葉の一部が白く変化する点。
これは花への訪問者を引き寄せるためのサインであり、植物の生い茂る山の中でも比較的見つけやすい特徴です。
また、日本だけでなく中国や朝鮮半島、ロシア極東地域など東アジア一帯に生育しており、古くから地域の自然の一部を形成してきました。
猫に作用する成分は、果実や枝、葉、つぼみなど複数の部位に含まれています。
特に実や粉末は作用が強く、猫に与えると反応が顕著に表れることがあります。
一方で枝や葉は穏やかな効果で、猫用のおもちゃなどに利用されるケースもあります。
猫がマタタビに反応する理由
猫がマタタビに夢中になるのは、主に「マタタビラクトン」や「アクチニジン」という成分の影響です。
これらは揮発性の物質で、猫の嗅覚受容体を刺激し、脳内の快感物質に作用することで一種の陶酔状態を引き起こします。
反応の仕方は猫によって異なります。
体を床にこすりつける子もいれば、ゴロゴロと喉を鳴らしてリラックスする子、さらには急に活発に動き出す子もいます。
このように行動に個性が出るのも、マタタビの面白い特徴です。
統計的には、成猫の約50〜70%が反応するといわれています。
ただし、子猫や高齢猫はほとんど影響を受けないことも。
これは、嗅覚や神経系の成熟度が関係していると考えられています。
マタタビの楽しみ方は?
なんとなくマタタビを食べ物のように考えている方もいるかも知れませんが、実際には匂いを嗅ぐだけで十分に効果を発揮します。
マタタビの成分は揮発性が高いため、粉末を食べたり枝をかじらなくても脳に作用します。
もちろん、かじって成分を口に含むことで効果が強まる場合もあり、その楽しみ方は猫それぞれ。
いずれにしても、例えば近づいただけでその影響が及ぶことは覚えておきましょう。
マタタビは人にとってのお酒とは別物
マタタビの効果はお酒に例えられることもしばしば。
確かに、気分が高揚したりリラックスしたりする点では似ています。
しかし、決定的に違うのは持続時間と作用の仕方です。
アルコールは体内に吸収されて長時間影響を与えますが、マタタビは嗅覚刺激による一時的な反応にとどまります。
マタタビの効果は通常5〜15分ほどで自然に収束します。
その後は、たとえマタタビが目の前にあっても反応しなくなり、数時間〜半日程度はクールダウン期間に入ります。
泥酔や依存につながることはなく、人でいえばアロマの香りでリラックスする感覚に近いと言えます。
マタタビのリスクやデメリット
基本的に安全とされるマタタビですが、いくつか注意すべき点もあります。
まず大きなリスクは消化器系のトラブルです。
マタタビの粉末や実を過剰に摂取すると、下痢や嘔吐を引き起こすことがあります。
特に粉末は成分が強いため、与える場合はほんの少量で十分です。
次に、「興奮しすぎるケース」です。
普段は穏やかな猫でもマタタビの作用で急に走り回ったり、他の猫にちょっかいを出すようになったりすることがあります。
多頭飼育では喧嘩につながることもあるので、与えるタイミングや場所には配慮が必要です。
また、依存性はないとされていますが、あまり頻繁に与えると「マタタビがないと遊ばない」といった行動パターンが固定されることがあります。
あくまでご褒美やリフレッシュの機会として、ごくまれに少量を与えるのが理想的です。
匂いだけで楽しむ場合は安全?
先述の消化器系のトラブルは、猫が粉末や実を口に入れたときに起こるものです。
そのため、匂いだけで楽しむ場合にはほとんど心配はいりません。
マタタビの揮発性の成分を嗅覚で感じ取るだけなら胃腸に負担がかかることもありません。
ただし、興奮しすぎるケースについては、匂いだけでも起こり得るため注意が必要です。
マタタビは猫の暮らしのスパイス
マタタビは、古くから猫にとって特別な存在であり、日本の自然の中で身近に見られる植物です。
その成分が猫の嗅覚を刺激し、一時的に陶酔状態を引き起こすことで、リラックスやストレス発散の効果をもたらします。
ただし、与えすぎは消化器系のトラブルや興奮のしすぎにつながるため注意が必要。
正しく取り入れて、愛猫の暮らしをより豊かにしてあげてください。
- 2025.09.29