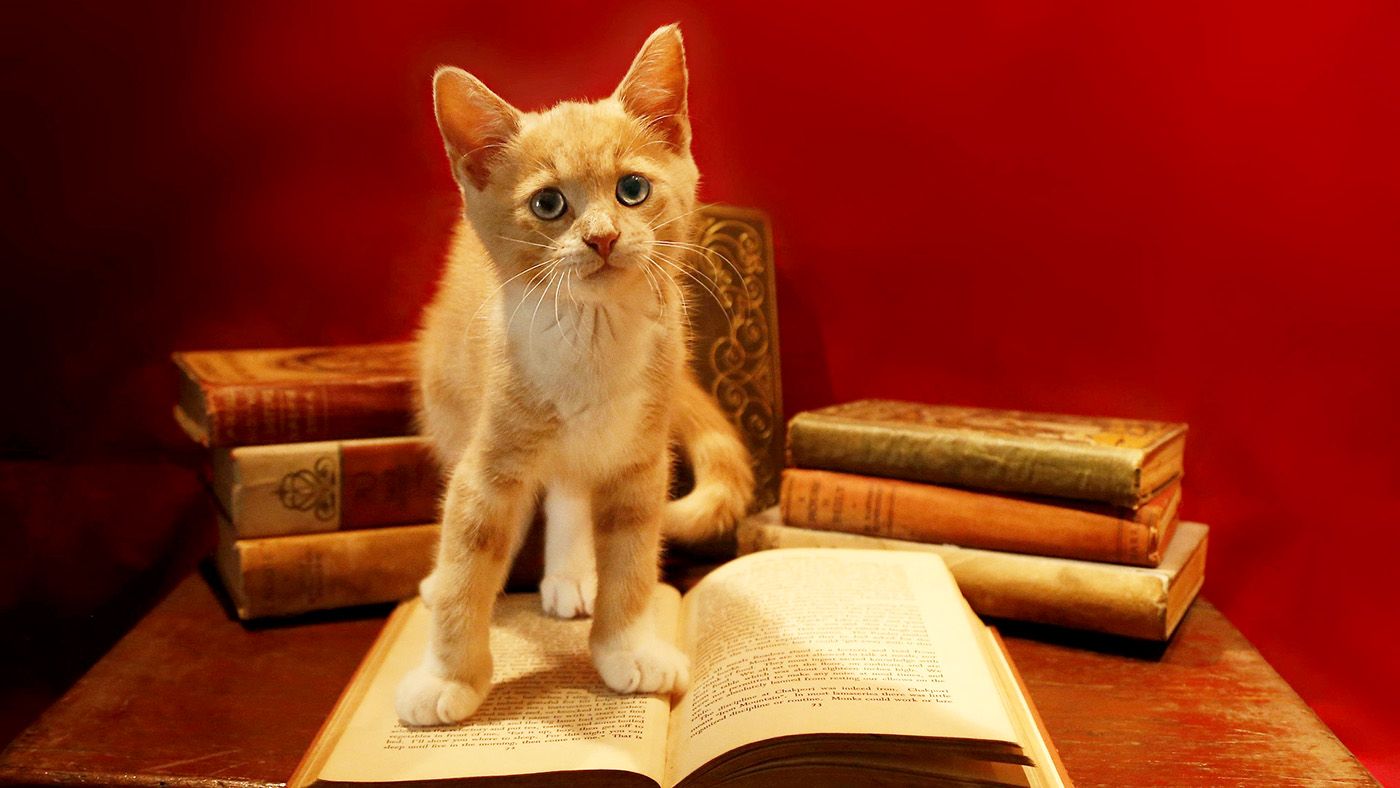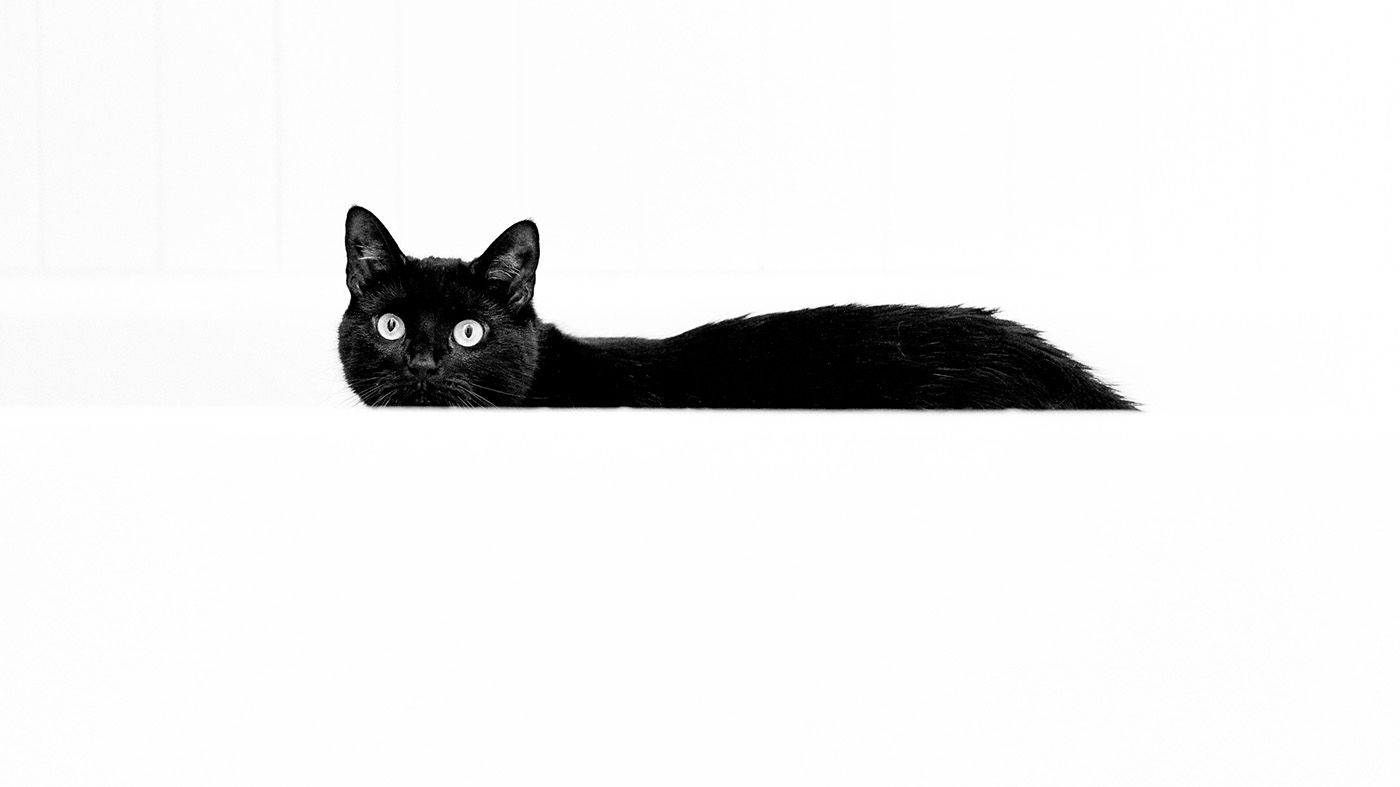化け猫と猫又 猫から生まれた未知と情念の怪異譚

日本の妖怪伝承のなかで、猫ほど多彩に描かれてきた動物はいません。
夜の闇に光る瞳、しなやかな動き、どこか人の心を見透かすようなふるまい。
そんな猫は、古くから「神聖かつ妖しい存在」として人々に恐れられ、敬われてきました。
そして、その最たる例が「化け猫」と「猫又」。
両者はともに「長く生きた猫が妖力を得て変化する」という点で共通しています。
しかし、その姿や性質、そして物語の舞台には明確な違いがあります。
今回は、化け猫と猫又の起源と代表的なエピソードを辿ってみましょう。
山に棲む古代の妖猫「猫又」
猫が妖怪として登場する最古の記録は、鎌倉時代後期に書かれた「元亨釈書(げんこうしゃくしょ)」にあります。
そこには「信濃国にて、猫が人を食う。これを猫またといふ」と記されており、すでに「猫又」という語が登場しています。
当時の猫又は、山に棲み、人を襲う恐ろしい妖怪でした。
夜の山道で炎をともすように現れ、旅人を惑わす。
その尾は二つに分かれ、火を吐き、人語を解し、人の霊を操ると信じられていました。
中世の山岳信仰と結びついたこの存在は、人々にとって「山の神の化身」でもありました。
時に祟りをなす恐ろしいもの、時に山を守る霊獣として、自然への畏怖が猫又の姿に重ねられたといえるでしょう。
猫又の代表的なエピソード
ある山では、夜になると二股の尾をもつ巨大な猫が火を吐き、行き交う人を飲み込むと恐れられました。
退治に向かった武士が猫を討ち取ると、その腹の中から人骨が現れたそうな。
このような物語は、山に対して当時まだ多く残されていた未知の畏れ、獣への恐れを象徴しています。
また、猫又を退治した名残りが地名になった例も多く、たとえば福島県会津の「猫魔ヶ岳」はその代表。
この山の伝承では、猫又を退治した武士の矢が岩を貫き、その血が岩を染めて「猫魔の淵」ができたと語られています。
人の心に棲む妖し「化け猫」
一方で、「化け猫」という言葉が広まるのは室町から江戸時代にかけてのこと。
この頃、人々の生活は都市化し、猫は家で飼われる身近な存在になりました。
その結果、妖怪譚の舞台も山から人里へと移り、猫は「人に化けて現れる」存在として語られるようになります。
化け猫は人間の姿をとり、しばしば女性として登場します。
特に江戸の芝居や浮世絵では、「美しい女性に化けて舞う猫踊り」などが人気を博しました。
その背景には、猫のしなやかな動きや気まぐれな性格が女性的な魅力と重ねられ、怪異というものがある種のエンタメとなった文化的感覚がありました。
こうした化け猫譚では、猫が人間的な感情を持つことが多く、恨み、嫉妬、恩返しなど、情念の物語として描かれます。
まさに「人間の心を映す鏡」としての妖怪、それが化け猫だったといえるでしょう。
化け猫の代表的なエピソード
江戸時代に大流行した「鍋島の化け猫騒動」は、化け猫伝説の代表格。
佐賀藩鍋島家で、理不尽に殺された女性の恨みを受けた猫が妖力を得て人に化け、復讐を果たすという筋書きです。
この物語では、猫が亡き女性の姿を取り戻し、夜な夜な屋敷に現れては主を悩ませます。
人々は正体を見抜けず恐れおののきますが、ついに剣客が障子越しの影を見て猫であることを見破り、退治します。
その後、猫の亡骸を弔うために「猫塚」が建てられ、祟りを鎮めると騒ぎはぴたりと収まりました。
舞台や芝居では「猫が女性に化けて踊る」場面が人気を博し、江戸文化の象徴的存在にもなりました。
猫が神となる――祟りから守りへ
猫又も化け猫も、最初はただただ恐れられる存在。
しかし、その祟りを鎮めるために祀られた猫塚や猫地蔵は、次第に守り神として信仰の対象となっていきます。
長野県や新潟県の山間部には、今も「猫又神社」「猫地蔵」などの小祠が点在し、「病を治す」「火事を防ぐ」「家を守る」などのご利益が語られています。
恐怖の象徴だったはずの猫のあやかしが、やがて感謝と祈りの対象へと変わっていきました。
祟るものも祀れば守り神となる。
この日本特有の発想が、猫又・化け猫を単なる怪談にとどめず、文化的・信仰的な存在へと昇華させたのでしょう。
猫が化ける日本人の心
猫又と化け猫。
いずれも長い年月を生きた猫が変異したと信じられ、畏れられた怪異。
未知への恐怖に名前を与え、克服しようと生まれた猫又も、身近な不条理を笑い飛ばそうと生まれた化け猫も、日本人が隣人たる猫に託した社会の写し鏡そのものです。
今なお私たちを魅了してやまない猫たちは、これからも多くの物語を生み出していくでしょう。
- 2025.11.04