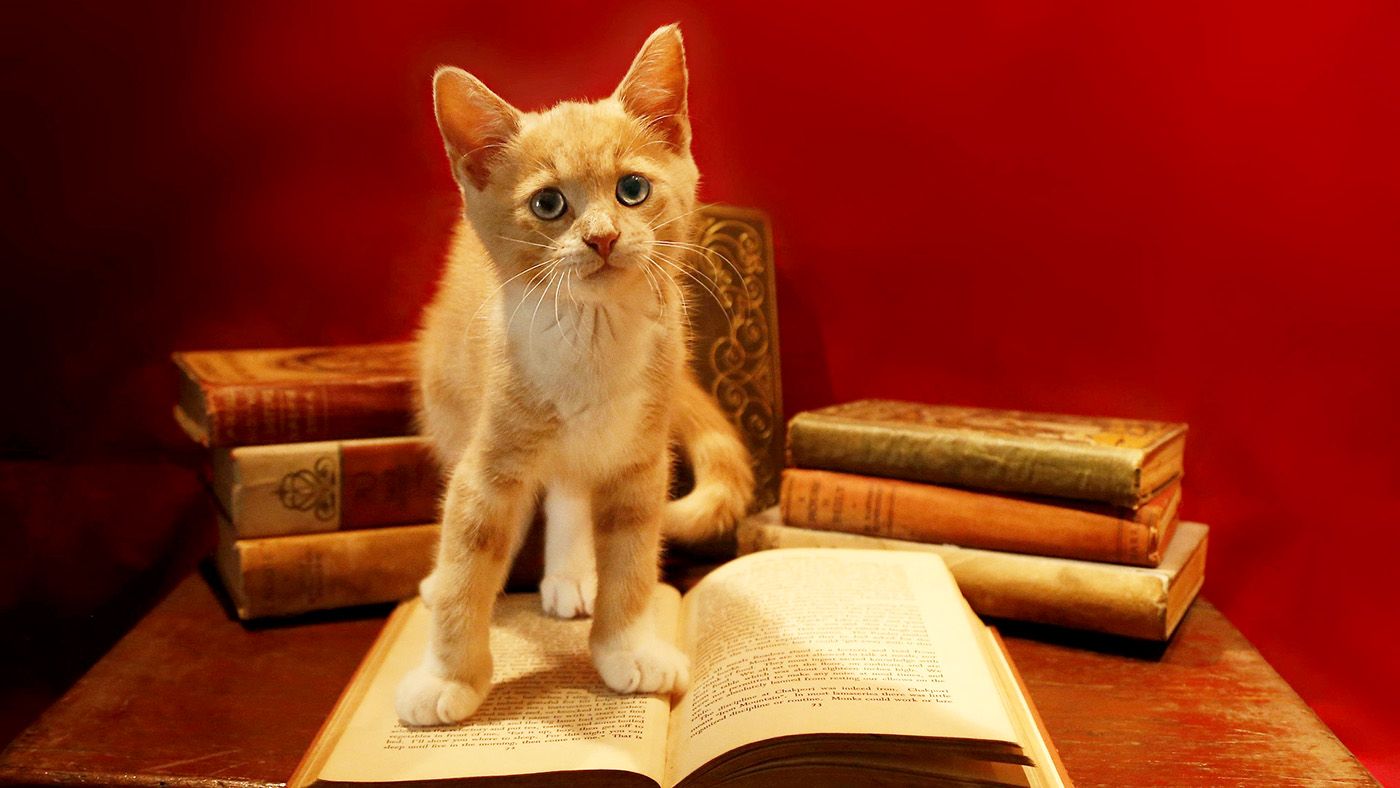伝統の土佐闘犬の今 土佐犬の文化と命をつなぐ挑戦

土佐闘犬(とさとうけん)という言葉には、実はふたつの意味が込められています。
ひとつは、土佐藩(現在の高知県)で育まれてきた「闘犬興行」という文化。
もうひとつは、そこから生まれた大型犬種「土佐犬(Tosa)」という犬種そのものです。
この「文化」と「犬種」の二層構造を正しく理解することこそが、歴史への敬意と動物福祉の両立につながります。
文化としての土佐闘犬

土佐闘犬の起源は、なんと戦国時代にまでさかのぼります。
戦を前に士気を高めるために犬を闘わせたという記録があり、江戸時代には土佐藩の庇護のもと、興行としての形が整いました。
やがて、土俵や番付、口上といった相撲文化を取り入れた独特の様式が確立されます。
この時期に、地域に伝わる四国犬をベースに、マスティフやグレート・デーンなどの洋犬を掛け合わせて作出されたのが、現在の「土佐犬」です。
つまり、四国犬とは全く別の系統を持つ犬種として分化し、その目的も「狩猟」ではなく「闘犬」としての強さと落ち着きを重視して固定化されました。
闘犬文化のこれから

土俵に犬を登壇させ、横綱格の犬が所作を披露するスタイルは、多くの人々の目を引きました。
しかし、その勝敗は「吠えたら負け」「逃げたら負け」などの行動の解釈によって判定され、犬にとっては心理的・肉体的な負担が大きいものでした。
現代においては、こうした行為が動物虐待に該当する恐れもあるとして、社会の受け止め方は大きく変わりつつあります。
日本では動物愛護管理法が強化され、自治体によっては闘犬興行を条例で禁止するケースも。
観光地として知られた常設施設も相次いで閉鎖されています。
さらに、海外では土佐犬の飼養自体を制限または禁止している国もあり、国際的な目は年々厳しさを増しているのが現状です。
闘わない「土佐犬」

では、土佐犬文化を終わらせるべきかといえば、当然そうではありません。
これまで膨大なリソースを投じて犬たちと向き合って得られた知見、「闘犬」という特殊な環境で得られた情報は、これからの動物福祉の観点でも必ず有益なものとなるからです。
大切なのは、「闘わせない形で犬と文化をどう守るか」です。
記録としての継承
土俵入りの作法、番付の言葉、犬と人の関係のあり方。
これらは文書や映像、音声、そして口述史として継承していくことが可能です。
特に言葉や所作に宿る「意味」は、教育コンテンツや地域資料として未来に引き継ぐ価値があります。
土佐犬という犬種の再定義
土佐犬という犬種を残すために、その繁殖においても倫理的な基準が求められます。
股関節疾患や心疾患の検査の公開、近親交配の防止、引退犬の終身ケアの徹底など、サステナブルな繁殖体制を整えることが欠かせません。
「強い犬」ではなく、「健やかに長く生きられる犬」こそが現代に求められる強さといえるのではないでしょうか。
トレーニング技術の継承
闘いというもっとも高い興奮状態が予想される環境においても、土佐犬が失わない落ち着きや協調性、ハンドラーとの信頼関係。
こうした特性は、闘いではなく共生の中でこそ活かしたい資質です。
そのための技術や体系、独自の方法論などは、犬種を超えて求められる重要な技術となります。
犬の幸福と文化の保存の両立

今を生きる犬の幸福を最大化する。
この原点に立ち返れば、土佐闘犬の象徴だった「力」も新たな意味を持つはずです。
闘い傷つける力ではなく、自分を律する力へ。
土俵や番付、化粧まわしといった伝統的なシンボルも、現代的な価値観と融合することで新たな価値としていけるはずです。
そして何より、土佐犬の血統を守ることが「闘わせない文化継承」として実現できるのなら、それは犬たちにとっても、地域にとっても幸せなことではないでしょうか。
- 2025.09.02